- Augus-Site
- 格闘技
- 大相撲
- 大相撲略史年表
格闘技/相撲/大相撲略史年表
このページは書きかけの文章です。
相撲:目次
ページ内目次
奈良・平安時代
古代、『古事記』に書かれている歴史については、書事体の信憑性に各方面から疑問視する声もある。また、本コンテンツは、下記出典資料を基に作成されており、現在の相撲協会の認識では古事記を含まないとしていることから、コンテンツに載せておりません。
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 皇極天皇元年 | 642,07/22 | 百済 |
| 養老三年 | 719,07 | 抜出司 |
| 神亀三年 | 726 | 聖武天皇が、前年の凶作を機に伊勢大廟(いせだいみょう?:現在の伊勢神宮のこと?)をはじめ二十一社に勅使 |
| 天平六年 | 734,07/07 | <続日本紀>によれば、この日聖武天皇が相撲戯をご覧になる、とあり天覧相撲の最初の記録である。 |
| 貞観十一年 | 869,04 | <貞観格式>に相撲節儀を制定する。 |
| 承安四年 | 1174,07/27 | 高倉天皇の天覧相撲(相撲節)が15年ぶりに開かれたが、源平の争乱 |
鎌倉・室町・安土桃山時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 文治五年 | 1189,04/03 | 源頼朝が、鎌倉八幡宮において将軍上覧相撲を観覧する<吾妻鏡>。 |
| 室町時代 | 1333~1573 | このころから、諸大名が相撲を見物するようになる。また、相撲を主題にした能楽/狂言が武家や民衆の間で好まれるようになる。 |
| 室町時代 | ~1573 | 室町時代の末期より職業相撲が発生する。 |
| 元亀元年 | 1570,03/03 | 織田信長が、狛江・常楽寺で上覧相撲を観覧する。 その後、豊臣秀吉、秀次の時代でも上覧相撲が行われた。 |
| 文禄五年 | 1596 | 関西の職業相撲団(の十人ばかり)が、九州筑後に巡業<義残後覚>。 |
江戸時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 慶長十年 | 1605,07/23 | 山城醍醐(寺?)で勧進相撲が行われた<義演准后日記 |
| 正保二年 | 1645,06 | 京都・糺森 |
| 慶安元年 | 1648 | 辻相撲・勧進相撲を禁止する触れが出される。勧進相撲興行に際して、浪人・俠客(きょうかく:昔のヤクザ)らの争闘が増えたため。 |
| 貞享元年 | 1684~1719 | 江戸深川・富岡八幡宮の境内で雷権太夫(年寄)が興行を許可され、勧進相撲興行が再開される。 しかし、これ以降しばしば辻相撲の禁止令が出る。 |
| 元祿十二年 | 1699,05 | 京都・岡崎天王社(おかざきてんのうしゃ)にて、勧進相撲興行が再開される。 <北小路日記(大江俊光記)>: 子番付の記録として最古のもの。三役の名称を初めて見る。 |
| 元祿十五年 | 1702/04 | 大坂の堀江勧進相撲公許興行行う。大坂の番付の最初。 |
| 享保九年 | 1724,06 | 東京・深川八幡社地興行行われる。江戸相撲興行の記録。 |
| 寶曆七年 | 1757,10 | 江戸相撲の組織が整い始め、江戸相撲独特の縦番付が始めて発行された。(京都・大坂は横番付) |
| 寶曆十一年 | 1762,10 | この場所の番付から、勧進相撲から勧進大相撲と記すようになる。 |
| 寛政元年 | 1789,11 | 谷風梶之助と小野川喜三郎に吉田司家(大相撲の宗家で、代々「追風」の号を名乗る)より横綱土俵入り免許する。横綱の始まりといわれる。 |
| 寛政九年 | 1759,05 | 柏戸宗五郎訴訟事件: 伊勢ノ海襲名(相続)問題。 |
| 文化二年 | 1805,02/16 | 春場所中、「め組の喧嘩事件 |
| 天保四年 | 1833,10 | この場所より、本所回向院(ほんじょえこういん:浄土宗の寺)が定場所となる。 |
| 嘉永四年 | 1851,02 | 嘉永事件発生:相撲史上初の同盟罷業(どうめいひぎょう:ストライキ)。 本中力士(前相撲と序の口の間力士)百余名が、回向院念仏堂に籠城し、中改め(現在の審判委員)を務めていた秀の山と相撲会所に取り組み日数の不公平を抗議した。結局は本中力士たちの殺気により、会所の幹部が回向院に駆けつけ要求に応じ、秀の山を説得し詫びさせ丸く収まった。 |
| 嘉永七年 | 1854,02 | ペリーの黒船再来航した際に、横浜にて力士一同米俵を運び怪力を誇示した。 |
明治時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 慶應四年 | 1868,04/17 | 明治天皇 |
| 明治二年 | 1869,03 | 大坂相撲は、江戸時代より続いていた横東西二枚番付を江戸風の縦一枚番付に改めて発行した。 |
| 1868,06 | 版籍奉還(明治2年6月17日:旧暦) | |
| 明治四年 | 1871 | 現在の大阪府は「坂」を「阪」に改称。 |
| 1871,03 | 京都において初の三都合併相撲を興行する。 | |
| 明治五年 | 1872,12/03 | 太陽暦(グレゴリ暦)の導入により、この日を明治六年一月一日とした。 |
| 明治六年 | 1873/11 | 高砂浦五郎が、遡る事1868年(慶応4年)に会所を牛耳っていた年寄玉垣・伊勢ノ海の横暴ぶりに抗議し、250名の力士の連判状組織しており、一部改善は見られたが、玉垣らはこれを反故していた。沈黙を守っていたが、1873年岐阜巡業にて多くの力士の賛同を得て名古屋に陣を構えたが、ミイラ取りがミイラとなり会所からは除名され、番付面から名を消された。 これに対し「改正相撲組」を組織した。 |
| 明治十一年 | 1878/02/05 | 警察庁より『角觝並行司取締規則』が発布され、力士・行司・年寄は営業鑑札を受けるようになる。 |
| 1873/05 | 会所(東京)は『角觝営業内規則』を制定。高砂の改正相撲組を復帰して合併し、別に小番付を発行。 | |
| 明治十九年 | 1886/01 | 『角觝営業内規則』を『角觝仲間申合規則』と改正。 |
| 明治二十年 | 1887/05 | 『角觝仲間申合規則』を『角觝組中申合規則』と改正。 |
| 江戸時代よりの“相撲会所”を「東京大角觝協会」と改称(二十一年、二十二年説もある)。 | ||
| 明治二十三年年 | 1890/01 | 初代西ノ海(第16代東横綱:高砂部屋)が、初めて番付に横綱の文字が記載される。 |
| 明治二十九年 | 1896/01 | 中村楼事件:一昨年の六月場所の東横綱西ノ海と西前頭筆頭鳳凰戦において物言いがついたが、高砂親方(西ノ海の師匠)が足跡を手で払い消したことが発端となり、西方力士が反発し事態は混乱していた。 西片力士大関大戸平はじめ三十三名が、協会(高砂)に対し激告文を送り改革を迫った。 この件を機に高砂は取締の座を追われ権力を失う。 |
| 明治四十年 | 1907/08 | 常陸山、門弟三名を連れ欧米漫遊、翌四十一年三月帰朝 |
| 明治四十一年 | 1908/05 | 『大角力組合新規約』十八カ条を定め、興行収入の合理化をはかる。 |
| 明治四十二年 | 1909/02 | 横綱の称号を従来の「最高級力士」を「最高位置の力士」と改称し、地位であることを明文化した。 |
| 1909/06 | 両国の回向院境内に国技館開館(両国国技館)。 これにより、江戸時代より続いていた晴天十日間興行が、晴雨にかかわらず十日間興行と定められた。 | |
| 個人優勝制度と優勝額の掲額を定める。東西対抗の優勝制度となり、優勝旗をつくる。 | ||
| 投げ纏頭 | ||
| 明治四十三年 | 1910/01 | 大阪力士大木戸の横綱問題で東京・大阪両協会絶交する。 |
| 1910/07 | 朝鮮・満州へ初の相撲巡業 | |
| 明治四十四年 | 1911/01 | 新橋倶楽部事件:場所前に給金値上げ問題で幕内および十両力士が新橋倶楽部に籠城。 |
大正時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 大正元年 | 1912/11 | 東京・大阪両協会が和解。 |
| 大正三年 | 1915/06 | 梅ヶ谷・西ノ海一行のアメリカ巡業 |
| 大正七年 | 1918/01 | 靖国神社境内にて春場所興行(以後三場所)。 |
| 大正十年 | 1921/05 | 国技館は資本金六十万円の株式会社組織となる。 |
| 1921/06 | 大錦・栃木山一行のハワイ・アメリカ巡業 | |
| 大正十一年 | 1922/01 | 株式組織を解散。制度を旧に戻す。 |
| 大正十二年 | 1923/01 | 三河島事件:場所前の力士会で養老金の増額など決議し、協会に要求し三河島に籠城する。 |
| 1923/09/01 | 関東大震災で国技館炎上、全焼する。 | |
| 大正十三年 | 1924/01 | 春場所を名古屋にて十日間興行。 |
| 大正十四年 | 1925/04 | 赤坂・東宮御所において、前年久邇宮良子女王様とご結婚した摂政宮殿下(後の昭和天皇)の誕生日を祝し台覧相撲を行う。
その際の下賜 |
| 1925/09/30 | 東京大角力協会より財団法人設立を申請 | |
| 1925/12/28 | 文部省より財団法人設立申請が認可され、「財団法人大日本相撲協会」が誕生。 | |
| 大正十五年 | 1926/01 | 大阪角力協会最後の本場所を台北で興行する。 |
| 1926/07 | 従来の東京・大阪両協会は解散し、大日本相撲協会結成の調印が、大阪市の大阪角力協会取締小野川宅にて行われた。 | |
| 1926/10 | 東西連盟相撲(第二回)(第一回は、大正14年11月および大正15年3月の二回に分けて開催された)を大阪で開催。 ルール改正:
従来は相手力士休場の際は両力士とも休みとなっていた。 | |
| 1926/10/23 | 明治神宮の土俵開き。 |
昭和時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 昭和二年 | 1927/01 | 東西両協会が正式に合併し、「大日本相撲協会」の名称となる。 |
年四回本場所を興行し、春夏の東京場所のほか三月・十月は地方本場所(関西本場所)を設ける。 | ||
年寄定員八十八名に大阪方十七名(うち二名は一代年寄)を加え定員百五名に増員する。 | ||
| 1927/03 | 大阪で晴天十一日間の本場所興行。 | |
| 1927/10 | 京都で晴天十一日間の本場所興行。 | |
| 昭和三年 | 1928/01 | ラジオの実況中継放送開始。 これに伴い、仕切り線の設定、仕切り時間の制限が決められた。また、全員が十一日連続出場となる。 |
| 1928/03 | 名古屋で晴天十一日間の本場所興行。 この場所から、不戦勝者も土俵で勝ち名乗りを受けることになった。 | |
| 1928/10 | 広島で晴天十一日間興行。 これ以降、地方本場所は番付を発表せず、直前の東京場所番付をもってする。 | |
| 昭和四年 | 1929/03 | 大阪本場所、晴天十一日間興行。 |
| 1929/09 | 名古屋仮設国技館で十一日間本場所興行。 | |
| 昭和五年 | 1930/03 | 大阪本場所晴天十一日間興行。 |
| 1930/10 | 福岡仮設国技館で十一日間本場所興行。 | |
| 昭和六年 | 1931/03 | 京都仮設国技館で十一日間本場所興行。 |
| 1931/04 | 天覧相撲を機に、二重土俵を一重に改め、土俵を大きくし、土俵屋根を神明造(しんめいづくり)にする。 | |
| 1931/05 | 横綱・宮城山の引退で、明治二十三年五月以来初めて番付面から横綱の名が消える(以後、昭和七年十月まで続く)。 | |
| 1931/10 | 大阪本場所晴天十一日間興行。 | |
| 昭和七年 | 1932/01 | 春秋園事件: 相撲道改革を唱え西方・出羽海一門の力士が、大井町・春秋園に籠城したため、一月場所の興行ができなくなった。 |
| 1932/02 | 残留力士による改正番付を作成し、東西制を廃止し、一門系統別部屋総当り制で八日間興行する。 | |
| 1932/03 | 名古屋で晴天十日間本場所興行。 | |
| 1932/10 | 京都で晴天十一日間本場所興行。 | |
| 昭和八年 | 1933/01 | 脱退力士の大半が帰参したため、別途番付を作成し、二枚番付として発表。 |
| 1933/02 | 脱退組は大阪に「関西相撲協会」を結成。 大日本相撲協会はこれを機に地方本場所を廃止し、春夏二回の東京本場所に戻る。 | |
| 昭和十二年 | 1937/05 | 十三日興行となる。 |
| 1937/12 | 「関西相撲協会」解散。 | |
| 昭和十四年 | 1939/01 | 一月場所四日目、双葉山は安藝ノ海(あきのうみ)に敗れ連勝が69でストップ。 |
| 1939/05 | 十五日興行となる。 | |
| 昭和十五年 | 1940/01 | 東西制復活、優勝旗旗手は関脇以下の最優秀成績力士があたる。 ちなみに、最後の優勝旗旗手は昭和22年(1947年)6月夏場所での東前8枚目でその場所から始まった優勝決定戦に勝ち残った力道山である。 |
| 1940/02/11 | 奉祝紀元2600年建国祭神前奉納大相撲開催(両国国技館) | |
| 1940/04 | 金村信洛(力道山)が二所ノ関部屋へ入門。 力道山の相撲時代の略史は力道山‐相撲時代‐を参照ください。 | |
| 1940/05 | 夏場所(4日番付発表・初日9日~千秋楽23日)東京・両国国技館にて開催 | |
| 1940/06 | 第七回大阪大場所(初日15日~千秋楽27日)大阪大国技館にて開催 | |
| 1940/07 | 満州巡業。満州場所(15日間)鞍山、撫順、奉天、ハルビン、新京で興行。 | |
| 1940/08 | 中国・北満州皇軍慰問巡業。 | |
| 1940/10 | 中国慰問巡業。 | |
| 昭和十六年 | 1941/05 | 一月場所前に制定した横綱一代年寄制を改正。 |
| 1941/02/05 | 帝国在郷軍人会大日本相撲協会分会結成 | |
| 1941/06/01 | 深川八幡境内歴代横綱碑の修築除幕式。 | |
| 1941/06 | 全組合による朝鮮巡業。 | |
| 1941/06 | 満州場所大相撲。 | |
| 1941/07 | 満州巡業。 | |
| 1941/10/25 | 吉田司家で羽黒山(不知火型)の横綱授与式。 | |
| 昭和十七年 | 1942/06 | 朝鮮巡業。 |
| 1942/12/28 | 東京・回向院で戦死した三段目力士橋詰正次、行司木村良雄の協会葬。 | |
| 昭和十八年 | 1943/02/13 | 相撲協会勤労報国隊結成。 |
| 1943/06 | 朝鮮巡業。 | |
| 1943/06 | 満州場所大相撲。 | |
| 1943/07/13 | 満州国皇帝陛下御前相撲(関東軍司令官邸)。 | |
| 1943/07 | 中国・満州皇軍慰問巡業。 | |
| 1943/11/05 | 学習院で皇太子殿下台覧相撲。 | |
| 昭和十九年 | 1944/02 | 国技館が軍部に接収され、風船爆弾工場となる。 |
| 1944/04/12-14 | 力士団が輸送戦線の荷役奉仕。 | |
| 1944/05 | 夏場所(初日7日~千秋楽23日)東京・後楽園球場。 | |
| 昭和二十年 | 1945/03/10 | 東京大空襲により国技館被災。各相撲部屋も焼失する。 |
| 1945/06 | 夏場所(初日7日~千秋楽13日)東京・両国国技館で非公開開催 | |
| 1945/08/15 | 終戦 | |
| 1945/11 | 戦後初の本場所(秋場所)を、被災破損した国技館にて、晴天十日間興行。 | |
| 1945/12/26 | 国技館が進駐軍(連合国軍最高司令官総司令部)に接収され、翌昭和21年9月24日改装修復し「メモリアル・ホール」と改称。 | |
| 昭和二十一年 | 1946/11 | メモリアル・ホールにて、十三日間の秋場所を興行。力道山新入幕する。 |
| 相撲くじ発売(この場所限り) 大蔵省・勧銀・相撲協会の協力により発売された。 | ||
| 昭和二十二年 | 1947/06 | 明治神宮外苑相撲道場で晴天十日間夏場所興行。 |
| この場所から各段ごとに同成績力士が優勝決定戦で優勝を争う制度が定められた。 幕内では9勝1敗が四力士いて四つ巴戦となる。東横綱羽黒山、西大関前田山、西張大東富士、東8力道山。 | ||
| この場所が東西制最後の場所となる。最後の優勝旗旗手は、優勝決定戦に残った力道山である。 | ||
| 1947/11 | 明治神宮外苑相撲道場で晴天十一日間秋場所興行。 | |
| この場所から、一門系統別部屋総当り制となる。(復活) | ||
| 殊勲賞、敢闘賞、技能賞の三賞を設定する。 | ||
| 昭和二十四年 | 1949/01 | 浜町仮設国技館で十三日間興行。(昭和十九年(1944年)春より五年ぶりの春場所復活) 浜町は、生井一家の縄張りで新田新作は関東国粋会系生井一家人形町貸元として博徒であり、新田組組長であった。新田新作は、戦時中から川崎の米軍捕虜施設に潜り込んでは米兵たちに野菜や酒を与えていたという。当時は、日本人ですら手に入れろことが困難な時代であった。新田建設という土建業も営んでおり焼跡の整理や強制疎開指定の建物の取り壊しを請け負っていた。戦後はGHQが名指しで復興を任された。当時の金額で3,000万円を投資し浜町に仮設国技館を完成させた。(この年の春夏の二回のみの使用で終わった) |
| 1949/05 | 浜町仮設国技館で十五日間夏場所興行。 | |
| 1949/10 | 大阪で十五日間秋場所興行。 | |
| 昭和二十五年 | 1950/01 | 蔵前仮設国技館で十五日間興行。 |
| 1950/05 | 横綱審議委員会発足。初代委員長は酒井忠正。 | |
| 1950/09 | 大阪で十五日間秋場所興行。 | |
| 昭和二十六年 | 1951/01 | 春場所十四日目に、大阪で吉田司家代表と協議した結果、長年にわたる司家の権限を変革する。 |
| 1951/05 | 前場所優勝の照國より優勝額が復活し、戦後初の掲額となる。 | |
| 年寄根岸家が廃家となる。 | ||
| 1951/06 | 年寄高砂が、八方山・大ノ海・藤田山と渡米する。 | |
| 1951/08 | 武蔵川一行がブラジル相撲協会の招きで渡伯する。 | |
| 1951/09 | 大阪で十五日間秋場所興行。 | |
| 昭和二十七年 | 1952/01 | 幟(のぼり)の復活。 明治四十二年一月の回向院以来四十三年ぶり。 弓取式は連日行うことになる。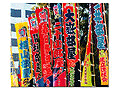 |
| 1952/04/28 | 同年二月二十八日に締結された日米行政協定に従い、日本国との平和条約が発効され、進駐軍(GHQ/SCAP)の占領が終わる。 ⇒メモリアル・ホールの接収を解除される。 | |
| 1952/09 | 四本柱の撤廃。代わりに吊り屋根に四色の房を下げる。 向正面東側:赤房、同西側:白房、正面東側:青房、同西側:黒房 | |
| 1952/10 | 明治神宮奉納全日本力士選手権大会復活する。 | |
| 1952/11 | 東冨士・朝潮の一行が沖縄へ初の巡業。 | |
| 1952/12 | 大阪において初の王座決定戦を興行。 | |
| 昭和二十八年 | 1953/01 | 春・夏・秋・冬の四場所制となる。春(三月)は大阪。 |
| 1953/02/01 | NHKが日本で始めてテレビ本放送を開始。 | |
| 1953/05 | テレビの実況中継放送開始。 | |
| 昭和二十九年 | 1954/09/18 | 蔵前国技館開館式挙行。また同時期に、相撲博物館も併設する。 |
| 昭和三十年 | 1955/03 | 第一回伊勢神宮奉納相撲を内宮で行う。 |
| 1955/05 | 天皇陛下 初の国技館来臨。 18年ぶりの天覧相撲。決まり手を68手と制定する。 | |
| 昭和三十一年 | 1956/01 | 昭和二十一年秋場所以来中絶していた前相撲制度を六日目から復活。 |
| 1956/09 | 昭和天皇御製記念碑の除幕式。 昭和三十年夏場所の天覧の際の御製「ひさしくも見ざりしすまひ人びとと手をたたきるる見るがたのしさ」(宇佐美宮内庁長官の書) | |
| 昭和三十二年 | 1957/01 | この年より十一月に九州場所を設け、年五場所制となる。また、本場所呼称は各月名を冠するものとする。 |
| 1957/05 | 新理事長に時津風就任。 | |
| 1957/07 | ルール改正:大関が三場所連続負け越したときは降下することに決定。 | |
| 1957/09 | 相撲茶屋名を廃止し、一番から二十番までの番号に改め、相撲サービス株式会社を設立。 | |
| 協会運営審議会を設置、会長・菅礼之助。 | ||
| 昭和三十三年 | 1958/01 | この年より七月に名古屋場所場所を設け、年六場所制となる。 |
| 「財団法人日本相撲協会」と改称。 大日本の「大」をとる。 | ||
| 十枚目以上の取組は、検査役の物言いの協議に短波マイクを使用することになる。 | ||
| 行司部屋の独立 | ||
| 1958/05 | 電光表示掲示板を新設、十枚目以上の勝負を明示する。 | |
| 1958/06 | 両国の旧国技館を日本大学に譲渡され「日大講堂」となる。 | |
| 1958/07 | 第一回熱田神宮(名古屋)奉納横綱土俵入り。 | |
| 行司の年寄襲名制度を廃止。 | ||
| 昭和三十四年 | 1959/01 | 木村庄之助・式守伊之助両家を年寄名から除く。 |
| 1959/09 | 横綱一代年寄制廃止。 ただし、引退後五年間は年寄名跡なしでも年寄として委員待遇を受けることができる。 | |
| 昭和三十五年 | 1960/01 | 行司定年制実施と共に、行司定員制も実施。副立行司の廃止。 |
| 決まり手を70手と改定。 | ||
| 若者頭、世話人、呼出の名が番付より消える。若者頭、世話人、呼出、床山、職員の定年制も決定。 | ||
| 年寄定年制が決定、施行は翌昭和三十六年一月一日とする。 | ||
| 1960/05 | 昭和天皇・皇后おそろいでの天覧相撲。 | |
| 1960/09 | 国技館の優勝額満額となり、先に掲額されたものより順次下ろす。 | |
| 弓取式終了まで勝負検査役は席にいることになる。 | ||
| 1960/12 | 財団法人設立三十五周年記念式典を国技館にて挙行。 | |
| 昭和三十六年 | 1961/05 | 力士の控え座布団は、各個人用のものをやめる。 |
| 昭和四十年 | 1965/01 | 部屋別総当り制の実施(一門系統別の廃止)。 |
| 検査役の物言い協議に使用していたマイクをやめ、協議の経過を正面検査役から発表係を通じて説明することになる。 | ||
| 1965/07 | 名古屋・金山体育館より愛知県体育館に会場変更。 | |
| 出羽海取締役を団長に、大鵬、佐田の山、柏戸、栃ノ海の四横綱、三大関ら幕内力士一行四十八名は二十五日ソ連へ出発。モスクワ、ハバロフスク公演。⇒八月十日帰国 | ||
| 昭和四十一年 | 1966/07 | 勝ち力士が行司から賞品を受ける場合、必ず手刀を斬って受ける。 |
| 昭和四十三年 | 1968/01 | 総理大臣賞新設。 幕内優勝力士に贈る |
| 1968/02 | 理事、監事は立候補制とし、連記制を単記制に変更する。 | |
| 取締制度を廃止。 | ||
| 勝負検査役の名称を、審判委員と改める。 | ||
| 1968/12 | 時津風理事死去、国技館にて協会葬。新理事に武蔵川就任。 | |
| 昭和四十四年 | 1969/01 | 横綱審議委員会委員長に舟橋聖一就任。 |
| 1969/05 | 勝負判定についてビデオを参考資料として使用する。 | |
| 1969/07 | 大関は連続二場所負け越して関脇に降下、翌場所十勝以上で大関に復帰できると改正する。 | |
| 1969/08 | 大鵬の三十回優勝の功績に対し、“大鵬”の一代年寄名跡を特別に認め九月場所初日土俵で表彰することが決まる。 | |
| 昭和四十五年 | 1970/02 | 一月場所後、蔵前国技館の改修工事着手。 |
| 昭和四十六年 | 1971/03 | 力士の控え座布団復活する。 幕内のみ。 |
| 1971/06 | 取組編成要領を制定。 幕内下位でも大きく勝ち越した力士を横綱、大関と取り組ませることができることとした。 | |
| 1971/08 | 第一回全国中学校相撲選手権大会を蔵前国技館にて開催する。 | |
| 昭和四十八年 | 1973/04 | 日中国交正常化を記念し、武蔵川理事長を団長とする幕内・十枚目力士全員が中国を訪問。北京、上海で相撲公演。 |
| 1973/05 | 行司部屋を解散し旧に復する。 | |
| 昭和四十九年 | 1974/02 | 新理事長に春日野就任。 |
| 1974/11 | 九州・福岡スポーツセンターより九電記念体育館に会場変更。 | |
| 昭和五十年 | 1975/12 | 財団法人設立五十周年記念式典を東京会館にて挙行。 |
| 昭和五十一年 | 1976/01 | 横綱審議委員会委員長に石井光次郎就任。 |
| 1976/07 | 君ヶ浜他二名は、ブラジル相撲協会の要請で相撲指導のため渡伯。 | |
| 昭和五十六年 | 1981/06 | 春日野理事長を団長とする幕内・十枚目力士全員、メキシコシティーにて相撲公演。 |
| 1981/09 | 横綱審議委員会委員長に高橋義孝就任。 | |
| 1981/11 | 九州・九電記念体育館より福岡国際センターに会場変更。 | |
| 昭和六十年 | 1985/01 | 新国技館落成式。(新・両国國技館) |
| 北の海の功績に対し、一代年寄名跡を認める。 | ||
| 1985/06 | 春日野理事長を団長とする幕内・十枚目力士全員、ニューヨークにて相撲公演。 | |
| 1985/12 | 財団法人設立六十周年記念式典を国技館にて挙行。 | |
| 昭和六十一年 | 1986/10 | 春日野理事長を団長とする幕内力士、パリにて相撲公演。 |
| 昭和六十二年 | 1987/02 | 新理事長に二子山就任。 |
平成時代
| 和暦 | 年月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 平成二十一年 | 2009 | 国技館100年記念。夏場所の前4月21日より6月19日に相撲博物館では「国技館100年」の展示が行われた。 |